今シーズン初めてのニッポンバラタナゴの稚魚が浮上しました。その成長の様子を浮上から5日間にわたって観察することができましたので紹介したいと思います。下記リンクにて動画も公開していますので、興味ある方は是非ご視聴ください。
1.稚魚育成水槽を使用したニッポンバラタナゴの繁殖
まずは、我が家におけるニッポンバラタナゴの繁殖方法を説明します。
以前に下記リンクの記事にて、我が家のニッポンバラタナゴ繁殖環境を紹介していますが、我が家では、タナゴの産卵床となる二枚貝(ドブガイ)を、親タナゴの飼育水槽に投入して産卵させています。
タナゴの産卵から稚魚が浮上するまでの期間は約3週間と言われていますので、まずは、親タナゴの飼育水槽にドブガイを3週間投入して親タナゴに産卵させます。

そして、3週間経ったら飼育水槽からドブガイ取り出し、稚魚が浮上する可能性のある3週間を稚魚育成水槽(写真)に移動させて稚魚の浮上を待ちます。(それを、2匹のドブガイをセットにして4匹のドブガイでローテーションしています。)
また、稚魚育成水槽で稚魚の浮上を待っているドブガイには、屋外で作成したグリーンウォーターを与えてその中の微生物を餌として摂取してもらっています。
グリーンウォーターにどれだけの効果があるか?はわかりませんが、そこで栄養を少しでも蓄えてもらって、次の飼育水槽投入に備えてもらうという考え方ですね。
なお、タナゴの繁殖は、いかに二枚貝を死なせずに産卵床としての役目を果たさせるか?が一番のポイントです。二枚貝を死なせずに飼育できれば、タナゴは自然に増えてくれます。
なお、稚魚を稚魚育成水槽内で浮上させる理由は、親タナゴの飼育水槽で稚魚が浮上すると、親タナゴが稚魚を食べてしまうと言われているからです。(メダカといいタナゴといい、自らの種族の赤ちゃんを食べてしまうなんて最低ですねw)
2.今シーズン初のニッポンバラタナゴの稚魚が浮上!
今シーズンは、繁殖に備えて比較的早くからドブガイを投入していた我が家のニッポンバラタナゴ水槽。(ドブガイ購入時の選び方や飼育方法などは下記リンクの記事をご参照ください。)
親タナゴが産卵する様子は確認出来ていたのですが、肝心の稚魚がドブガイから浮上してきません。親タナゴの飼育水槽から稚魚の育成水槽にドブガイを移してもうすぐ3週間…半ばあきらめかけていた時。今シーズン1匹目の稚魚の浮上を確認しました。
経験上、浮上した稚魚が最もお亡くなりになりやすいのは、浮上したその日、及びその翌日です。一般的な魚における産まれたての稚魚は、お腹の膨らんだ部分にヨークサックという栄養分を持って生まれてくるので、すぐに餌を捕食する必要はありませんが、タナゴの稚魚は孵化して2週間くらいは二枚貝の中でじっとして過ごすので、二枚貝から浮上する頃にはヨークサックの栄養分を使い切っています。
よって、浮上したての稚魚はすぐに餌が捕食できないと餓死してしまいますので、細心の注意を払ってケアをする必要があります。
我が家の稚魚育成水槽では、前述したとおりドブガイの餌としてグリーンウォーターを投入しています。メダカのビオトープにグリーンウォーターを投入すると、餌を与えたときのようにメダカたちが活発に動き出しますので、グリーンウォーターには魚に取っても良質の餌になる微生物が含まれていると思っています。当然ながら、それが浮上したてのタナゴの稚魚にも良質な餌になると考えていますので、浮上してすぐはグリーンウォーターを多めに投入するようにしています。
もちろん、粒が極小の市販の飼料も与えます。市販の餌の中では、メダカ稚魚用餌が最も粒が細かいと思っているので、それをホントに少量ずつ(袋に指を突っ込んで、指先に付くくらいの量を)与えていきます。まあ、浮上してすぐはなかなか市販の餌を食べてはくれないので、食べ残しの餌で水質が悪化しないように底床に溜まったごみは小まめにスポイトなどで取り除く必要があります。(稚魚育成は手間がかかりますね。。。)
3.浮上したてのニッポンバラタナゴ-5日間の成長観察
それでは、浮上した稚魚の様子を確認していきましょう。
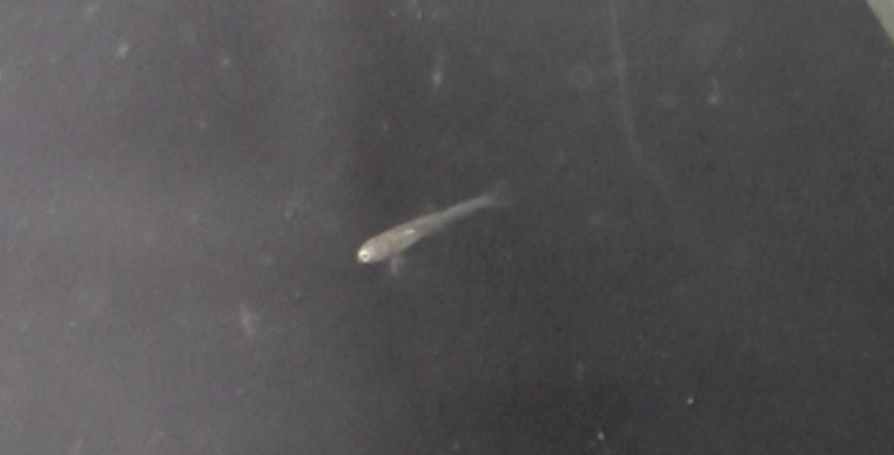
稚魚の1日目の様子は…やはりちょっと泳ぎが下手ですね。浮上した(外界に出た)ばかりなので、泳ぎが下手なのは当たり前ですが、こちらが心配になるくらい、ゆったりとして元気のない泳ぎでした。(次の日まで頑張れるかなぁと若干不安を抱くレベルでした)
2日目。まずは稚魚の泳ぐ姿を確認し、ほっと胸を撫でおろしました。ただ、泳ぎの方は1日目とあまり変わることはなくぎこちないです。まあ、稚魚の元気な姿を見れただけで良しとします。
3日目。生存を確認して餌を与えるだけで撮影などをする時間がなかったのですが、2日目より少し元気に泳ぎ回っている様子が見受けられました。
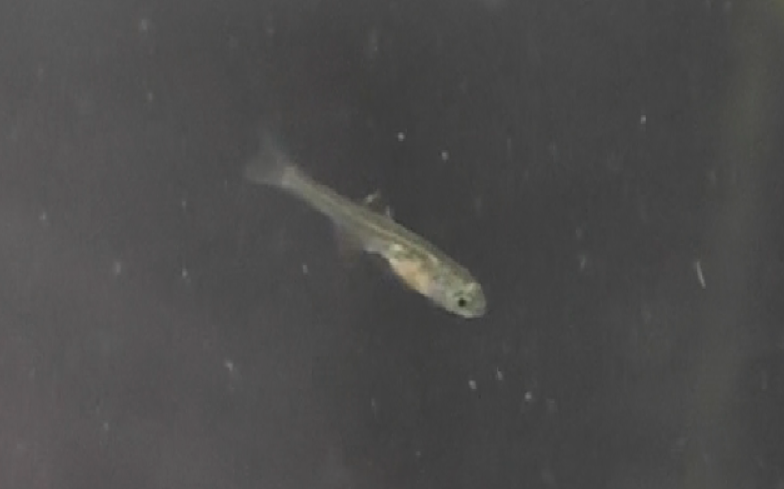
4日目には、背びれに黒い模様をつけたタナゴらしい風貌に変わりました。泳ぎも機敏になってきて実にタナゴらしくなってきました。
タナゴ類は過去にドブ川のような川で釣れたこともありますので、元来とても生命力の強い魚なのだと思っています。タナゴが数を減らしている理由は、環境の悪化そのものではなく、産卵床となる二枚貝が数を減らしていることが原因です。(カワニナがいなくなると生息ができなくなる蛍と同じですね。)
なお、稚魚のお腹は少し膨らんで見えますので、口から栄養を摂取することは出来ているようです。経験上、ここまで育ってしまえば、よほどの理由がない限りお亡くなりにはならないはずなので、ちょっと安心してお世話することができますね。

5日目です。ちょろちょろと自由に泳ぎまくって元気いっぱいになりました。お腹もさらに膨らんだように見えます。
ただ、1日2日遅れで他の兄弟たちも浮上してくると信じて観察していましたが…他に浮上して来る子がいないのはちょっと寂しいですね。この子には歳の離れた上の子として元気に生きていってもらいましょう。(長男か?長女か?は、私にはまだわかりませんけど。)-のちの観察で長女であることが判明しました-
・今シーズン初の稚魚を観察しての感想
ドブガイ投入からはちょっと時間がかかってしまいましたが、やっと1匹の稚魚を浮上させることができました。とりあえずは一安心ですが、他の稚魚が浮上して来ないのは、私の飼育方法に何らかの問題があるんでしょうね。。。
成魚の飼育水槽から、稚魚の育成水槽にドブガイを移動させるときに環境の変化で貝の中の稚魚がお亡くなりになる??稚魚水槽でドブガイが殻を閉じていることが多かったために、中の稚魚が酸欠などでお亡くなりになった??原因はいろいろと考えられますので、今後も色々と問題点を改善しながら、繁殖にトライしたいと思います。

今現在、親タナゴの飼育水槽に投入したドブガイが、投入してから3週間が経過しようとしております。そろそろ稚魚の育成水槽に移動させるタイミングとなりますので、まずは移動の際の水合わせをしっかりやって、失敗要因と考えられる項目を一つずつ潰していきたいと思います。
単純に、産卵管を挿入していたけれど卵が産み付けられていなかった!や、精子の放出が不十分で受精卵になっていなかった!などが原因だと改善の術がありませんが、次の育成ターン(3週間)は少しでも多くの稚魚が浮上できるよう、しっかり飼育していきたいと思います。
とにもかくにも。タナゴたちが群れをなして泳ぐ姿はとてもかわいいです。産卵が近くなると争いが始まってしまいますが、それ以外はとても仲良く泳いでいます。今シーズンはたくさんの稚魚を育成して、もっと大きな群れになった様を観察したいですねー。(眺めながらお酒が呑めますw)
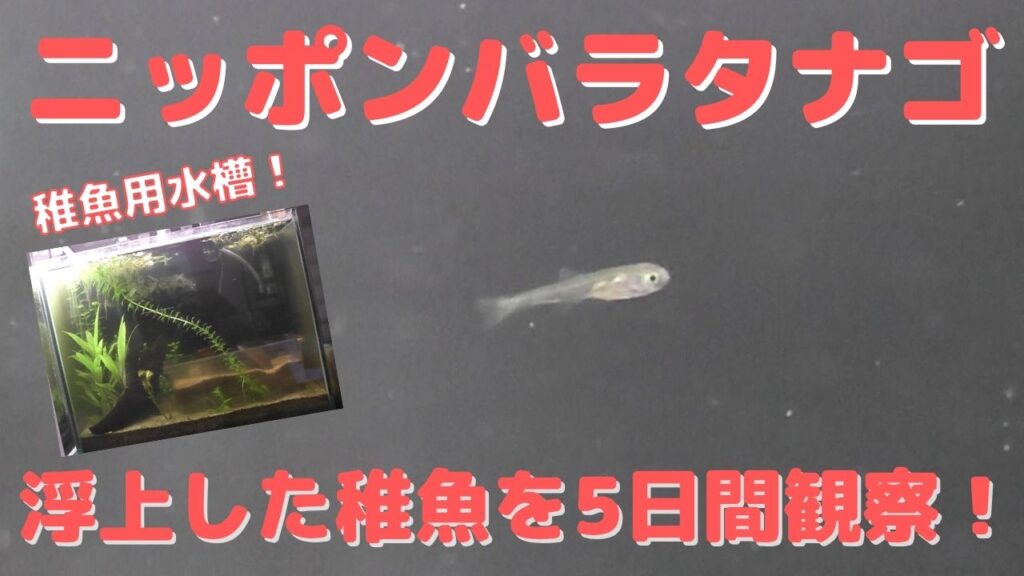





コメント